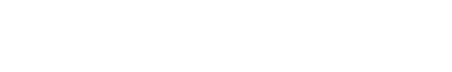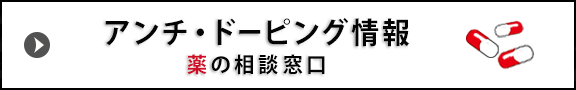ダイビングの歴史
ダイビングの発祥は、その昔海賊がヨーロッパに出没していたころ、船員がマストから海に飛び込んで遊んでいたというのが始まりであるという説やハワイの原住民が滝壺の上から飛込んで遊んでいたというような記録から水遊びに端を発するという説など、いくつか存在している。しかしながら、現在行われているような競技としてのダイビングがいつ頃から行われるようになったかという正確な記録は残っていない。ドイツにおいて飛込みの演技の種類や型が創案されたと書き残されているが、その年号も明らかではない。しかしながら、スウェーデンやドイツにおいて、現在のダイビング競技の前身が認められ、当時の機械体操の選手がトレーニングでの場として床より安全で柔らかい水面を利用したという記録が残っている。これが、近代ダイビングの歴史である。
その後、体操選手が独立し、体操の練習のために行っていたものから積極的にダイビングに取り組むようになってダイビングが発展し、世界最初のダイビングの競技会は、1886(明治19)年のドイツ水泳選手権で飛板飛込みが行われていたとされている。後、1890(明治23)年には、イギリスがスウェーデンのダイバーを招いて競技会を開催した。当時は単純に足からか、頭から水中に飛び込むだけという競技ではあったが、これが世界最初の国際競技大会であった。
そして、14年後の1904(明治37)年の第3回オリンピック・セントルイス大会では高飛込みが正式種目として採用され、4年後のロンドン大会からは飛板飛込みも行われるようになった。
その後、競技施設や演技種目が著しく発達し、特に1924(大正13)年の第8回オリンピック・パリ大会頃から、ダイビングはめざましい発展をとげた。
二度の世界大戦を経験したヨーロッパ各国の低迷期の後、アメリカがダイビングの強国となり旧ソ連、中国のめざましい台頭がみられるようになって現在に至っている。ダイビングはオリンピックごとにルールの改正と施設の改善が繰り返されながら進歩してきた。
このような歴史の中、第18回オリンピック・東京大会を境にダイビングの一つの流れが大きく変わってきた。その前のローマ大会までは美しさを表現する芸術的要素が競技の中心であり、技もそれほど複雑ではなく比較的単純であったものが、東京大会から回転や捻りがより多く演技に取り入れられるようになり、複雑で高度な技を追求するという別の流れへと進んだのである。
それ以後、年々演技種目の高難度化が進み、第22回オリンピック・モスクワ大会の頃からは飛板の性能のめざましい向上の助けもあって、現在では最高が前宙返り4回転半の宙返り、捻りが4回転半という技が認められるまでに進歩してきた。近年の五輪ではさらに、技が究極化し、複雑な演技として発展を続けている。代表的な演技として、前宙返り2回半、3回捻り(5156)や前逆宙返り2回半、2回半捻り(5255)が有名である。
また板・高、各競技種目においても、観客が見て楽しむ競技として発展した2人同時に飛び込むシンクロダイビングも正式種目として行われるようになった。
その後、体操選手が独立し、体操の練習のために行っていたものから積極的にダイビングに取り組むようになってダイビングが発展し、世界最初のダイビングの競技会は、1886(明治19)年のドイツ水泳選手権で飛板飛込みが行われていたとされている。後、1890(明治23)年には、イギリスがスウェーデンのダイバーを招いて競技会を開催した。当時は単純に足からか、頭から水中に飛び込むだけという競技ではあったが、これが世界最初の国際競技大会であった。
そして、14年後の1904(明治37)年の第3回オリンピック・セントルイス大会では高飛込みが正式種目として採用され、4年後のロンドン大会からは飛板飛込みも行われるようになった。
その後、競技施設や演技種目が著しく発達し、特に1924(大正13)年の第8回オリンピック・パリ大会頃から、ダイビングはめざましい発展をとげた。
二度の世界大戦を経験したヨーロッパ各国の低迷期の後、アメリカがダイビングの強国となり旧ソ連、中国のめざましい台頭がみられるようになって現在に至っている。ダイビングはオリンピックごとにルールの改正と施設の改善が繰り返されながら進歩してきた。
このような歴史の中、第18回オリンピック・東京大会を境にダイビングの一つの流れが大きく変わってきた。その前のローマ大会までは美しさを表現する芸術的要素が競技の中心であり、技もそれほど複雑ではなく比較的単純であったものが、東京大会から回転や捻りがより多く演技に取り入れられるようになり、複雑で高度な技を追求するという別の流れへと進んだのである。
それ以後、年々演技種目の高難度化が進み、第22回オリンピック・モスクワ大会の頃からは飛板の性能のめざましい向上の助けもあって、現在では最高が前宙返り4回転半の宙返り、捻りが4回転半という技が認められるまでに進歩してきた。近年の五輪ではさらに、技が究極化し、複雑な演技として発展を続けている。代表的な演技として、前宙返り2回半、3回捻り(5156)や前逆宙返り2回半、2回半捻り(5255)が有名である。
また板・高、各競技種目においても、観客が見て楽しむ競技として発展した2人同時に飛び込むシンクロダイビングも正式種目として行われるようになった。
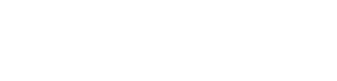
copyright (c)2013 Hyougo Swimming Federation All Rights Reserved.